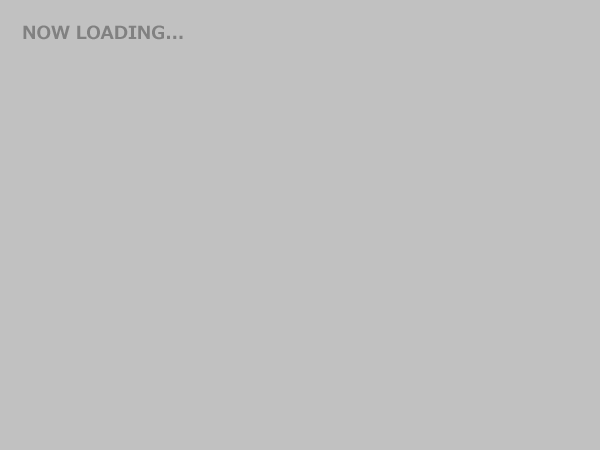園長の紹介 このページでは園長についてQ and A 方式で取り上げています。
自己紹介
- 氏名:平出 茂樹
- 1965年長野県生まれ。
- 最終学歴:東海大学工学部卒。当時、神奈川県秦野市に住んでいました。
- 以前の職業:機械設計。当時横浜市緑区に住んでいました。
- 以上、神奈川県民暦:約11年。
- 植物栽培暦:約50年。小さい頃からやってました。ストレリチア栽培歴は約40年、大分分かってきましたが、まだ分からない事の方が多い・・・?
- ストレリチア栽培の目的:育種、栽培技術の確立等。毎年交配を行っています。良い親株を選抜出来た事から、性質の良い株を作る事は特別では無くなった。新花色については無さそう。栽培については何も参考にしなくても対処出来るところまで来ている。
ストレリチア以外の得意植物 ・・・消去法の賜物
- 君子蘭、モンステラ、フィロデンドロン・セローム等の観葉植物、アロエ、シクラメン、蓮、睡蓮等水生植物全般、夜香木、レモン、水稲、ジャンボニンニク、トマト、大根、蕪、スイートコーン等の野菜。他にも幾つか・・・。
- 君子蘭は丈夫だったため結果として生き残った。その他、モンステラもアロエも同様。
- シクラメンは気候が合ったため生き残った。
- 水生植物は元々好きな植物だった。
- 夜香木は大きな木になると、ご近所まで香りが漂っていくほど強い香りに惹かれた。
- ジャンボニンニクは全部収穫したつもりでも必ず残っていて毎年出てくる。よって結果として残った。
- 水稲は元々日本の気候風土に合っている。よって、春に植えさえすれば、秋に収穫出来る。
- レモンはたまたま挿し木しておいたものが、良く育ち結実した。この出来事以来、スーパーでレモンを買う事は無くなった。果物屋でも買ってません?・・・。
- トマトは元々好きな野菜だった。
- 大根は種苗メーカーの、種子品質向上の影響が大きかった。
- 蕪は夏播きにしては害虫被害が少ないことから良く出来た。
- スイートコーンは多肥で追い込めば立派なものが収穫出来る。
※結局、得意と言うよりは、単にその植物が丈夫なだけ・・・と言う話かもしれません。
- 写真は観葉植物で有名なフィロデンドロン・セローム。白く見えるのは花です。モンステラの花に似ていますが、仏炎苞 の外側が緑色をしている。残念ながら種子は実らなかった。育て始めてから3~4年で開花しました。花が咲いたのはこの年と翌年の2回だけで木が大きくなっても咲かないのが謎です。
木で一つ選ぶなら・・・?
椰子の木:一級観葉植物でもある。熱帯情緒あふれるところが魅力。我が家にも育て始めて10年の広葉ケンチャヤシがありましたが成長点が腐って(ストレリチアの芯腐れの様な症状で)枯れました。・・・残念!ちなみにストレリチアの有茎種と椰子の形態は似ている。最初は葉数が増えると共に茎が太くなり、後に上に伸び始める。他に年輪が無い等。
※厳密には椰子は木ではありませんが、草でも無いので挙げました。
花以外で水性植物を一つ選ぶなら・・・?
河骨:薄く柔らかい水中葉が優雅で綺麗な事。これを水槽で長期栽培するのはこつが・・・。
おもしろい植物を一つ選ぶなら・・・?
食虫植物:暖地にいる大きなゴキブリを捕らえるハエトリソウ、小型ネズミを捕らえる位大きなモウセンゴケ又はサラセニア等が出来たら面白い。もし、本当に出来たなら、名前を変えなければなりません。ゴキブリトリソウ(取りそう)とか、ネズミトリソウとか・・・。
興味のある植物を一つ選ぶなら・・・?
花の香りの良いもの。最近気に入っているものは、Cyphomandra betaceae(1)(2)で、 ‘’Tree tomato‘’:トマトの木、‘’Tamarillo‘’:タマリロと呼ばれている本来は熱帯果樹扱いです。今まで経験した中で一番好みに合うかもしれません。次がトキワレンゲ、夜香木、レモンの木も良い香り・・・。一つじゃなかった・・・。
(3)は私が咲かせたユーチャリス、別名アマゾンリリーです。アマリリスに似た球根から大きな葉を数枚付ける。確かこの花も香りがあった様な気が。草そのものは比較的良く育てられるのですが、花がなかなか咲かなかったのを覚えています。性質的には葉焼けしやすく、氷点下の冷え込みで容易に枯れてしまう。
遮光下に置いてある植物を、寒さが予想されるときに取り込むことは気付きにくく、それで何回枯らしたことか・・・。
球根植物を一つ選ぶなら・・・?
百合、写真はカサブランカ。これは私が若かった頃咲かせたもの。当時は球根が高く大変でした。病害虫も多いので健康に育てるのに苦労しました。最初の2年位は何とか咲かせられますが、それ以上になると徐々に無くなります。姿、形、花の香り、色、日本が誇る代表選手。今は改良品種よりも、日本のヤマユリやたもとゆり、さくゆり等の方が気に入っている、百合以外ではシクラメン、カラー等。
多肉植物で一つ選ぶなら・・・?
アロエ:ストレリチアと原産地が同じため、同じハウスで栽培出来る。地植えなら何もしなくても生きている。時期が来ると、花が咲く。用途は色々。以前、木立アロエの小さな鉢植えを地に下ろしたらあっと言う間に伊豆半島で見た様な大きな藪になってしまって・・・。これを全て消費するほど怪我もしないし、困ったものです。今はサンゴアロエに軸足を移している。
果樹で一つ選ぶなら・・・?
西洋梨:甘さ、酸味、香り、三拍子揃い文句無し。過去には我が家にも、ラ・フランスやシルバーベルと言う品種がありましたが、害虫が付きやすいのが玉に瑕。何度か収穫出来たものの、結局無農薬栽培では木を維持出来ませんでした。残念!
熱帯果樹で一つ選ぶなら・・・?
チェリモヤ:世界の三大果物の一つ。日本の果物には無いおいしさ。カスタードクリームの様な・・・。実際に育てたこともありますが、耐寒性はありません。果実を成らすほど大きな木を維持する事を考えたら、それほどの情熱は無くあきらめました。また単に育てる事で選ぶならバナナか。ストレリチアに近いから比較的簡単。以前、中国原産の種有りの小型種を育てていた事があります。
野菜で一つ選ぶなら・・・?
:トマト、かぼちゃ、スイートコーン・・・決められない。
難しい野菜を一つ選ぶなら・・・?
ネットメロン:連作が出来ず、雨が掛かればうどん粉病が付き、雨よけハウスではハダニが付き、肥料をやり過ぎると実が付かず、控えすぎる過ぎると小玉になってしまって・・・。ただ、その果実の種子を蒔けば大体同じものが出来、種苗費が掛からないのが救いか。
日本が誇れる植物を一つ選ぶなら・・・?
盆栽:今更私が言うことは無し。他には菊、洋蘭、縄文杉等か・・・。
植物の良いところは?
文句を言わない。嘘をつかない。裏切らない。その他、今の言葉で言えば癒し系と言うことか・・・。他には気に入らなければ処分出来る事。
園芸の醍醐味は?
種から育てる事。:大きくなるまでのプロセスが面白い。種子の色形から将来の姿を想像しながら播いて、育てて、予想もしなかった様な花が咲いた時の喜びは大きい。今の人は完成しているものを求める傾向がある。特に植物に関心の低い人は・・・。
植物を手懸けていて喜びを感じる時は?
種子を得られた時。:園芸を始めた当初は「希望の品種の種苗を手に入れた時」でした。その後「開花した時」、野菜や果樹だったら「収穫した時」に、その後に「初めて蕾を出した時」に、後に「初めて花芽を付けた時」に、後に「播種後、苗を得られた時」に、後に実生で「発芽した時」に、現在は「良さそうな種子が得られた時」になりました。「結果」から「原点」に戻った感じ。
ストレリチアを本格的に始めた理由は?
思い道理に行かないから。:一般的な植物では、ある程度上手く行き出すと、その先を悟ってしまい、そうなると面白くなくなる。飽きると言うか。しかし、ストレリチアは、良い土に植えても、良い肥料を与えても、良い環境に置いてもすぐに大きくは変わらない。変わらないのなら何とか変えようと考えます。それで土でも肥料でも条件を変えてやってみる。その結果、少し良くなったとする。それで他にも条件を変えて行えば更に良くなるのではと考えて実行する。そうするとまた少し良くなったり、変わらなかったり、場合によっては失敗し、それでまた検証して何らかの条件で実行する。以降その繰り返し。その結果、以前より良い状態に近付いたり、方向ややり方等を間違えると上手く行かなかったりと、小さな成功と失敗を経験しているうちに手探り状態だったものに道筋が見えてくる。そこに引き込まれる。他の世界で例えるなら、先の分からない航海の舵取りを任された様な感じ。その他には自分自身との相性、何となく上手く行きそうだと思ったから。実はこの辺が一番重要かもしれません。実際にやっていて他の植物よりも面白い。
※人間と植物とは相性があります。人間関係と同じだと考えます。
ストレリチアの難しいところは?
品種改良と優良株の入手:花色は橙色、黄色以外は難しい。現実的に無理かも・・・。性質の丈夫さが変わったものが出にくい原因の一つかもしれません。また、ストレリチアは、研究が遅れていて優良種と呼ばれるものが少ない。自分の育てている在来系統が優良株と思っている人がいるかもしれません。
ストレリチアの上手な育て方
感謝の気持ちを持つこと。:決して自分の力でストレリチアをねじ伏せよう等と考えてはなりません。「王妃の身の回りのお世話を任せて頂いてありがとうございます。」と言う感謝の気持ちを持つ事です。(考え方の話です。)
ストレリチアの良いところは?
主役になる花である。:この花を切って花瓶に挿しておけば他に何もいらない。花がきりっとしていてプライドが高く、他を寄せ付けない迫力がある。中途半端な花を添えると、その花の方が劣って見えてしまう。脇役ではない事が重要。その他、性質が丈夫でなかなか枯れないところ。私の様な「ずぼら栽培家」向き。通常の園芸とは逆の考え方で、ストレリチアを枯らそうとします。つまり、水を与えないとか、大量に肥料を与えるとか、除草剤をかけるとか・・・。なかなか枯れません。他には堂々として花が無くても草姿は見栄えがする事等。
ストレリチアとは?
表現の一つ。美術の絵画、写真、音楽の楽曲等と同じ位置付け。:鈴木勇太郎さんは「自分自身の投影」だと仰っていました。
ジャンセアとは?
手の掛からないお客様!!
種から育て始めた当初は、出来るだけ短期間で花を咲かせようと張り切っていましたが、後にその気持ちは徐々に薄れて行きました。それ位大きく変わらない、毎日見ていても変化が感じられない。よって、必要最低限の面倒だけ見てやれば良い。夏場の半年位経過してから振り返って見て育ったかどうか判断するタイプの植物です。
写真は南アフリカ自生株から取った種子の実生による開花株です。この大きさで約10年掛かっている・・・が手は掛かっていない。
ちなみに現在は、播種後、鉢植え栽培で7年位で開花に持って行く事が出来ます。真面目にやれば?もう少し早いかもしれません・・・。